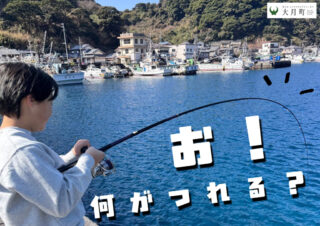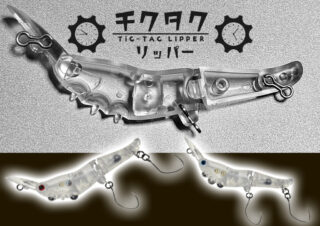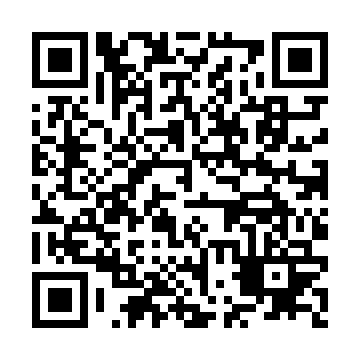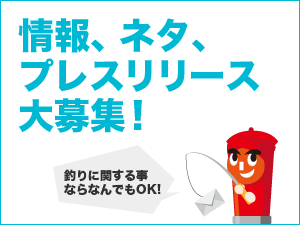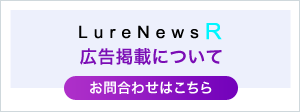釣りと幸せの話 ~釣りは何を釣るのか~
今日は少し、“釣りと幸せ”について書いてみたいと思う。
難しい話ではなく、僕が釣り人として生きてきた中で静かに積み重なってきた、そんな実感のようなものだ。

レオン 加来 匠(Kaku Takumi) プロフィール
釣りは何を釣るのか
まず冒頭に、僕の人生を方向づけた小さなエピソードから始めよう。
小学6年生のある日。父が僕を呼び止めて、こう聞いた。
「匠、釣りは何を釣るのか分かるか?」
10歳そこそこの僕は、深読みする発想もなく、「魚」と即答した。ところが父は首を横に振り、静かにこう言った。
「魚を釣るのは表面上の目的。 釣りは、心と体の健康を釣るんだよ」
この短い一言は、当時の僕にはさっぱり分からなかった。でも、胸の奥にそっと刻まれ、今日に至るまで消えない。
数年後、中学3年。思春期で悩みも増え、何かと揺れ動く年頃だった。その時、同じ質問を父から再び投げかけられた。僕は答えた。
「心と体の健康を釣るんだと教わりました」
その返答を聞いて父が残した次の言葉は、さらに深かった。
「匠よ、釣りは自分探しの旅だ。 30歳になっても、50歳になっても、60歳になっても思い出しなさい」
この二つの言葉は、70歳になった今でも僕の釣り人生の根っこにある。

日本人と釣りの“原点”
縄文時代の遺跡からは、貝殻を削って作られた U字型の釣り針 が出土しているという。
もしこの発見が真実なら、日本人は1万年前(〜とされる)の段階で、すでに“釣り”を高度に活用していた民族だと言える。四方を海に囲まれ、急峻な山がそびえ、それらをつなぐ川が無数に流れる日本列島。この地形そのものが、僕らを“釣りする生き物”として育んできたのだと感じる。
太古の海辺で貝や魚を獲って暮らしていた祖先の感覚(記憶)が、どこか奥底に刻まれているのかもしれない。事実、釣りとの出会いは人によって違うはずなのに、「初めて竿を握った瞬間にスッと馴染む」という経験を語る釣り人は少なくない。
もちろん全員が釣り好きではない。それぞれ背負って生まれた物は違う。でも、僕やあなたのように「どうしようもなく釣りに惹かれる」人間は、縄文のDNAとでも呼ぼうか、生まれ持った宿命・役目・あるいは個性のような物が確実にある。

沖縄での出土品

茅ヶ崎市堤貝塚出土品

宮城県田柄貝塚出土の鹿角製釣り針
現代──“魚を釣るための釣り”から、“幸せのための釣り”へ
アジングが楽しい。メバリングが楽しい。チヌ、キジハタ、どの魚も狙えば狙っただけ奥が深い。
でも、長く釣りを続けてきて、僕はひとつの核心に辿り着いた。釣りは、自分が幸せで居続けるための装置なんだ。魚を釣ることそのものより、海の匂い、波の音、風の冷たさ、竿越しのわずかな振動。これらの要素が、心の雑音をきれいに洗い流してくれる。
縄文時代の釣りは生きるための“漁労”、現代の釣りは“生きる質を上げるための行為”。
文明の発達による生活や環境変化と共に、釣りの目的そのものが少しずつ変化してきたのだろう。
ここでひとつの話を挟ませてほしい。
釣り人なら誰もが知る純文学作家・開高健。彼の著作「輝ける闇」は、ベトナム戦争の最中、メコン川周辺を取材した体験を元に書かれた作品だ。
バリバリッ、ドカン、パンパンパン……
まるで花火のように弾道が飛び交い、殺し合いが起きている。
開高健はその様子を撮るため暗闇の川辺へ走り出る。
すると、ふと視界に“異様な光景”が入る。
あれだけの戦闘音が響く最中、
こちら岸の安全な側では、
ひとりの老人が、まるで何事もないかのように竿を垂れていた。
…開高健「輝ける闇」より
僕はこの場面を読んだ瞬間、背筋がゾッとするほど心を掴まれた。
「こんな状況で釣りを? 自分があの場にいたら、竿を出せるだろうか?」
でも、開高健の描写を読んでいると理解できてしまう。その老人にとって、釣りは“現実から逃げる行為”ではなく、心の平穏を取り戻すための、生きるうえでの“確たる”バランス装置だったのだ。川の向こうで何が起きていても、自分の心を守るために竿を出す。
「俺は俺の幸せのために釣りをする」
そんな静かな、“釣り人”の生きる上での確たる意志を僕は感じた。この話は、僕の心に深く残っている。釣りという行為の本質を、残酷なほど鮮明に教えてくれる。

SNS時代──“釣果の呪い”に囚われないために
ここ20年で、釣りはSNSによって大きく姿を変えた。良くも悪くも、釣果や写真が常に可視化される時代になった。そのおかげで釣り人口が増え、情報も広まった。だが同時に…
・他人の大物に焦る
・自分が釣れないことに落ち込む
・「自分だけ思うように釣れない」と悩む
・他人の道具に嫉妬する
そんな人が増えた。
──でもね。釣りの目的は「自身が幸せになること」だと気づけば、苦しむ必要はない。釣りは他者との競争ではないし、他人の釣果はあなたの価値と本来無関係だ。自分が自分のためだけに楽しむための行為である事を、もっと鮮明にすれば何の問題も起こり得ない。
特にサイズの悩みについてはっきり言いたい。例えば僕は尺メバルを釣るのはそう難しくない。正しい場所へ、タイミングと釣り方を合わせて入れば釣れる事をすでに知っているから、釣れる時は比較的簡単に釣れてしまうからだ。
ただ、心が震えたのはそこじゃない。初めて投げたトップウォータープラグに、22cm程度のメバルがドカーンと出た日のあの感動。あれは30cmの大物より何倍も強烈だった。
理由は簡単だ。“釣りは、下手だった頃のほうが圧倒的に幸せを感じやすい”からだ。
失敗が多かった頃の一匹。
釣れない日の末にようやく出た一撃。
迷走しながら辿り着いた僅かな成果。
人は成長すると「できて当たり前」が増えていく。だから、ビギナー時代の喜びは二度と再現できない。そこには尊い“初体験の幸福”がある。大物が釣れない悩みは、実は「幸せの余白」なのだ。できれば下手なままの方が幸せであるかもしれないのだ。
そしていつの日か行き着く先は、“太公望”のように糸も針も付けずに竿だけを振込み、「ここへ投げてこう流せば…ほら来た!」と、イメージの中だけで完結させる高みまで行ける趣味であるのかもしれない。

釣り場が減っても、魚が減っても──楽しみ方は無限にある
近年、釣り環境は確かに厳しくなっている。
・釣り場の閉鎖
・混雑
・魚の減少
・ルールの細分化
・SNSでの摩擦
これらは現代の釣り人が避けられない現実だ。でも僕は悲観していない。むしろ、そこにこそ新しい釣りの可能性すらを感じている。
なぜなら、釣りは、楽しみ方を“自分で創造できる遊び”だから。
対象魚を変えてみる。
ジャンルを広げてみる。
釣り場を大きく変えてみる。
魚はどこにだっている。内水面の小魚にロマンを求めてもいい。かつて誰もやっていなかった釣り方を探してみてもいい。釣りは“枠”を外した瞬間に大きく広がるのだ。他人とは関係無く、自分の枠を探せば良い。
釣りは死ぬまでできる最高の遊び
僕の師匠は100歳まで釣りを続けた。
こんな趣味、他にはなかなか存在しない。体力が落ちても、年齢を重ねても、釣りはその人のペースに合わせて寄り添ってくれる。
日本は海も川も湖も全方位に揃い、餌釣りもルアーも、多種多様なジャンルが成熟している。縄文DNAによる、“釣りが好きになる体質を持って生まれた僕ら”は、やっぱりとても幸せなんだよ。

最後に──釣り人でよかった
人生は大変だ。
学業も、仕事も、健康も、家族も、社会も。誰だって心沈む日がある。でも、僕らにはだからこそ釣りがある。釣りは、心をリセットし、“元の自分”の場所へと連れ戻してくれる。
父の言葉を、今日さらに深く噛みしめる。
「釣りは心と体の健康を釣るもの」
「釣りは自分探しの旅」
この二つがしっかり腑に落ちれば、釣りで自分を傷つける必要はもうどこにもない。釣りは、僕たちを幸せにするために存在しているのだから。