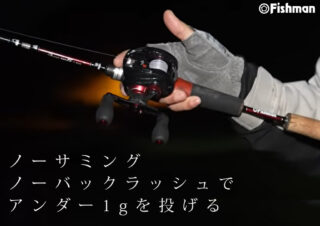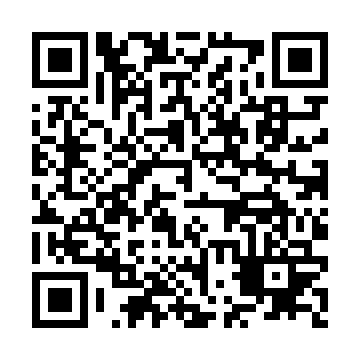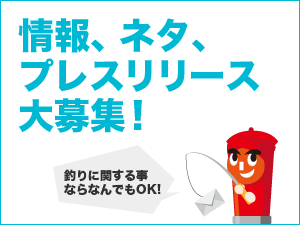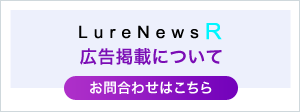春エギングの常識が変わった

現在でももちろんパターンは成立するが「春=藻場」というパターンは通用しにくかったり、相応の場所に巡り合えないというのが昨今の春エギング。
そう感じるようになったのは様々な要因があるが、全国的に広がる“磯焼け”の影響による藻場の減少。


かつて定番とされていたポイントに通っても、イカの姿が見えない。けれどその一方で、まったく藻場のない沈み根やブレイクライン、あるいは離岸流の絡むようなポイントでしっかりと釣果を出すアングラーが増えてきた。
イカの付き場が変わってきている…というよりも、産卵を意識した個体ではなく捕食を意識した個体に照準を合わせて狙うことが必要で、どのような状態のイカを狙っているかも重要なキーとなっている。
新たな狙い方の基準「地形 × 潮 × 回遊or固定」
産卵を意識したアオリイカ以外に春のアオリイカには2つのタイプがある。
ひとつは、潮通しの良いブレイクや沈み根に一旦足を止めて餌を獲ったりする定位する「回遊からの居着き型」。そしてもうひとつは、ベイトを追って沖から回遊してくる「回遊型」。

産卵を意識した個体は藻場が重要なポイントだが、今は“藻場”が少なくなっている分、根や潮目など捕食を意識した個体を狙った方が釣果に繋がりやすく、ポイントの選択肢も結果拡がる。
夜は回遊待ち、昼はストラクチャー撃ち。この考え方で狙い方を組み立てることで、より春の良型アオリイカと出会う確率が上がる。

カラー選びに「光のローテーション」を
環境変化は、カラー選びにも影響を与えている。
YAMASHITAのボディカラー理論である、「フラッシングの反射、ケイムラやネオンブライトの紫外線発光、自発光する蓄光ボディの夜光をローテーションする“光のローテーション”」。これは発光の強さや波長の違いによってイカに与える印象は大きく変わる。

例えば、“居着き型”には1対1の近距離戦が想定される。そのため、光の届く距離としては近距離戦を得意とする紫外線系やネオンブライト。一方、“回遊型”には遠くからでも発見しやすいフラッシングボディ。そして、潮色や光量のライトレベルに応じて夜光を投入していく。
この「光のローテーション」こそが、今の春エギングにおいて重要な戦略になっている。

最後に
「変化する環境に適応する」…これは、アオリイカだけでなくアングラー側にも求められる大事な視点。
藻場がなくても、イカはいる。イカの立場になって「どこに身を置き、どう動くか」を想像することで、自然とエギングの組み立て方も変わってくる。春の海に新たな視点を持ち込むことで、またひとつ“釣れるエギング”が見えてくるはず。

春のエギングは、一年で最も大型のアオリイカが狙える季節。フィールドに立てば潮の流れ、風のにおい、水の透明度とポイントの特徴を感じることができ、その一つ一つがイカとの出会いに繋がります。
少し視点を変えて、いつもとは違うポイントにエギを通してみるだけで、まったく新しい展開が待っているかもしれません。イージーではない、年々変化する春エギングですが、フィールドを読み解き、良型アオリイカを手にできた際の価値や喜びも魅力のひとつ。是非チャレンジしてみてください。