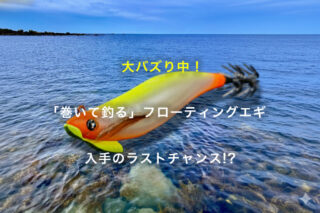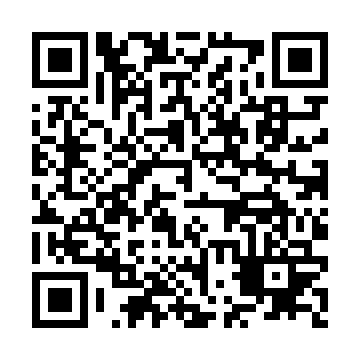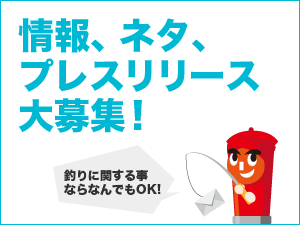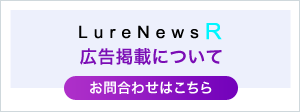今江克隆のルアーニュースクラブR「時代を変えたFFS(フォワードフェイシングソナー)の功罪と審判」 第1255回
アメリカのFFS規制
先日のTOP50桧原湖戦報告では衝撃的な新進若手達のFFS(フォワードフェイシングソナー※ライブサイトの米国式表現)技術レベルの高さと、自分のFFS能力の現在地について触れた。
このFFSに関しては、一時TOP50でも規制案が決まりかけるなど賛否両論だが、本場アメリカのB.A.S.Sエリートシリーズ、BPT(バスプロツアー)選手間での賛否両論は日本以上に激しいようで、今年のFFS装備規制に続き、「Blend tradition with technology(伝統とテクノロジーの融合)」という名目の元、エリートシリーズで来季からさらに厳しいFFS禁止規制が始まることが正式に決まったようだ。
B.A.S.S.が2026年エリートシリーズのライブソナールール変更を発表 – Bassmaster
今シーズンから適用されているエリートシリーズの発信機及びモニターサイズの設置規制に対し、BPTではすでに3ピリオド制の最初の1ピリオドのみFFS使用が許可され、残りの2ピリオドは使用が禁止される非常に厳しいものになっている。
そして驚いたことに来季、エリートシリーズでは9戦中4戦でFFS装備が全面禁止というさらに厳しいFFS規制を決めた。

来季、B.A.S.SでFFS(Forward Facing Sonar)の新たな厳しい規制が決まった。メインスポンサー企業の製品でありながら、エリートシリーズ9戦中4戦が完全にFFS使用禁止になったことは衝撃だ。
これがエリートシリーズのみの適用なのか、B.A.S.S全体に適用なのかはまだ不明だが、これは少なからず今後の日本のトーナメントにも大きな影響を与える可能性が高い。

今やTOP50で搭載していないプロはいないと言ってもよいFFSデバイス。エリートシリーズでの4戦全面使用禁止が決まった現在、TOP50での使用制限がどうなるのか予断を許さない。
昨年のBPTの規制決定には少なからず驚きを覚えたが、エリートの規制では基本的に大型モニターを多数設置することによる前方走行時視界不良に起因するボート事故等の発生によるところもあり、これ以上の規制はないと思っていただけに今回の決定は衝撃的だった。
一説によるとB.A.S.S選手会の提案によって決定したとも聞いたが、FSSデフォルト時代とも言えるアメリカのトーナメントでもFFSに反対する選手がそれほど多かったことのほうが驚きだった。

高速走行が多いアメリカでは巨大モニターの過剰搭載が安全面からも問題になっていた。だが、アメリカではFFS使用に反対するベテランプロが想像以上に多いようだ。
FFSの功罪
そこで今週は完全にトーナメントの時代を激変させたと言っても過言ではないFFSの功罪について検証してみよう。
まず最初に、FFSに関して自分は規制に関しては反対派だ。
それはスマホの使用を制限するようなもので、昔の魚探やGPSの進化の延長線にあるものであり、時代と共にバスフィッシングスキルの可能性を否定するものではないと思うからだ。

自分はFFS肯定派だ。今もバストーナメントに情熱を失わない一つの理由に、「全ルアー、全テクニックで最高峰トーナメントで勝つ」と言う昔からの自分の信条があるからだ。
確かにアナログ時代に比べ、サイドスキャン、360スキャン、そしてFFSの登場は、その圧倒的情報収集力から超難解複雑な湖底の桧原湖ですら、ものの1週間程度で全部把握できるほどのゲームチェンジャーになった。
さらにFFSは主流のGARMIN LVS34より発射電波がさらに強力なLVS62を使えば、半径60m(見つけるだけなら100mでも可能)の円の中のどこにバスが今、現在どの程度の群れを成して泳いでいるかも簡単に把握できてしまうし、ビッグディスプレイなら40m以上先の小さなルアーもモニターに捉えることも可能になる。
フラットなら状況が変わって群れが移動したり、水深が変化しても当日に短時間で移動先を見つけることも比較的簡単なのである。

今や1インチワームでもモニターに捉え、更には60m近い超遠距離射撃もTOP50では常識的なテクニックになった。FFSはトーナメントの世界を完全に別世界に変えてしまったと言ってもよい。
FFSだけが規制される理由
まあ、こう聞いてしまえば金があってFFS装備したら経験や地形や自然の読みなどカンケーねーじゃん…アホらし…と思うのも致し方ないだろう。
だが、GPS、サイドスキャン(SS)、360が登場した折にはこんな賛否両論大騒動にはならず、FFSだけが規制騒動になるには大きな違いがある。
それは固定型で受動的情報収集機であるSSや360に対し、FFSはその名の通り全方向の前方をリアルタイムで能動的に操作でき、自分の操作力次第でその能力に決定的な差を出せることである。
その差を決定づけるのが、実は極めてアナログなフィジカル差、最も重要なのが不安定な水上でエレキを片足で自由自在、それも振り幅10cm程度の精度で常に操作し続け、モニターにルアーとバスを写し続けられる脚力と体幹、同時にその画面に連動して寸分たがわずルアーを正確にタイミングよく投入操作できる距離感、操作力のコンビネーションである。
さらに言うなれば、そこに常日頃からデジタルデバイス機器操作に対する「習慣性」の差が決定的にものをいう。
ゆえにFFSはどんなに高額な機材を多数揃えても、それを使いこなす人間の能力差勝負になることは明らかな真実である。
このFFSをやり込めばやり込むほどに痛感するのは、FFSの能力差とは実にアナログ極まる肉体的操作技術の差だということだ。
能力差は年齢差
ハッキリ言って、その能力差は決定的に年齢差と言っても過言ではない。
事実、FFSがデフォルトになったここ数年、アメリカではベテラン強豪プロの引退が相次ぎ20代の新人が台頭、TOP50も50歳前後の選手の活躍がめっきり少なくなり、新人選手がいきなり初年度から活躍することが珍しくなくなった。
それほどFFSの能力差はフィジカル差に如実に反応する証明である。
ゆえにアナログ時代からのベテランプロにとっては自分たちの地位を脅かす最も難解で体力的にも「無理ゲー」な存在であり、若手にとっては慣れ親しんだ最強の時短情報収集兵器なわけで、そこに賛否両論が起こるのも理解はできる。
一般アングラー的には「金持ちのアソビ…」的な嫉妬感情や、釣り本来の原始的「野生の勘」を否定されることへの嫌悪感がFFSアレルギーを起こすのも不思議ではない。

高性能なエレキ、FFSデバイスの代表格であるGARMINの16インチを2台装備すると、350万円もの価格になる。もはや小型バスボートより高額な装備であり、20代の若者が自力で到底装備できる価格とは思えないだけに嫉妬ややっかみも多くなる。
FFSスキルでも負けたくない
では、なぜ61歳にもなる自分はアレルギーを起こさないのかと問われれば、40年近くあらゆるアナログ技術を経験してきた自分にとって「未知と最新への好奇心と興味がアレルギーを上回る」ということだ。
正直、すべてのキャリアを手にして同じことの繰り返しに少し飽きていた自分に、FFSを使いこなす若手の強さは強烈なインパクトと新鮮さ、下手すれば恥ずかしながら時代の最先端テクに対する「憧れ」みたいな気持を与えてくれたとも言えるかもしれない。
自分がトーナメントを始めた頃に最強無敵の田辺哲男さんに憧れたのと同じような懐かしい気持ちを、藤田京弥プロや青木唯プロにまた感じてしまったのだ。

自分がトーナメントを始めた頃一番憧れた田辺哲男選手。憧れがトーナメントへの最初の動機だった。となりは現・JB副会長の山下高弘氏。
そして年寄りの冷や水かもしれないが同じ舞台で、このFFSスキルでも負けたくないと言う気持ちが、今の自分の支えになっているような気がする。

自分がFFSに強い興味を持ったのが藤田京弥プロの理解不能なほど圧倒的すぎる強さだった。その強さに憧れるほど、新鮮で未知のFFSに強烈な魅力を感じた。
FSSスキルとアナログ(サイト)スキルの今後、バストーナメントの今後は?