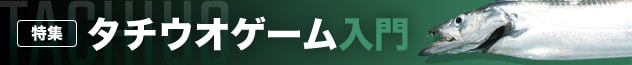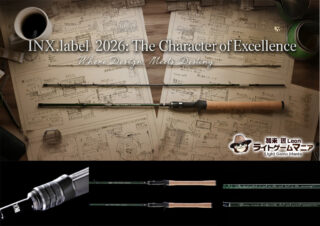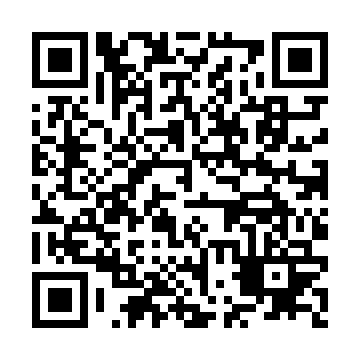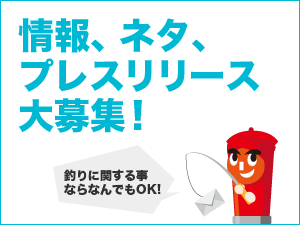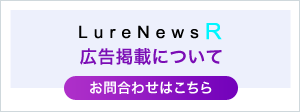あそこでは釣れ出した。
こっちにはまだ回遊してきていない。
といった会話が釣具店などで聞こえはじめると…タチウオシーズンの到来!

普段他の釣りをしていても、この季節だけはタチウオ釣りに集中するという方も多いことでしょう。夕方から夜に多くの釣り人が堤防に並ぶ光景も、この季節の醍醐味。

これだけ人気なジャンルであるからこそ、初めての方にはぜひ楽しんでもらいたいということで、今回は手軽に始められるショアからのタチウオゲームの基本を紹介!
タチウオの生態
タチウオを狙うのであれば、どういった魚なのかを知るべき!
という訳で、まずは生態について解説します。ショアのタチウオゲームでは、一般的に夜に釣れることが多いです。ただ、船では実際に昼間でも釣れていますよね?

昼間はベイトを捕食しやすい深場でじっとしており、夜になると岸に寄ってくるベイトを求めて活発に動き回ります。夜行性だという説もあれば、ベイトの動きにリンクしているだけで夜行性ではないという説も。どちらにしても、ショアから効率良くタチウオを狙いたいなら、時間帯的には朝マズメや夕マズメ、夜間に狙うのが一般的。

では、この時間帯に水中で何が起こっているのでしょうか? 実はベイトフィッシュが水中で回遊していて、実際に水面を観察すると釣り人の目でも確認することができます。そのベイトが目視できたり、タチウオがそのエリアでコンスタントに釣れているという前情報があれば、ベイトが「接岸」しているという証拠になります。
日中でもベイトを追い回してはいますが、「接岸」していないため、回遊を確認することはできません。それが夜になるにつれてベイトが岸へ寄ることで、タチウオも一緒に接岸し、初めて夜に釣れるという訳です。

ただ、夜ではないとエサを食べないというわけではなく、夜は浅瀬に上がってきやすいということ。深場でもベイトの動きにはリンクしているので、夜でなくてもある程度の水深があってベイトフィッシュさえ溜まっていれば、日中でも釣れる確率はあります。
しかし、それでは日によって場所が変わってしまうため、エリアを見つけ出すのが難しいです。そのため、夕暮れや夜、夜明けに狙う方が効率もイイでしょう。

アジ、サバ、イワシ、キビナゴなど。
タチウオの基本的なベイトは小型の回遊魚が多いです。
大型になるにつれて多くのカロリーを摂取する必要があるため、エリアによっても異なりますが、アジの群れや大きめのマイワシについているタチウオは比較的大型なことが多いです。また、コノシロの群れについていたり、大型のタチウオは小型のタチウオも捕食対象にしています。さらに、目線より上の魚だけでなく、ボトム付近のアナゴやハゼなども好んで食べる時期があるなど、小型回遊魚だけが捕食対象ではありません。

多くの釣り人が気になるはず、タチウオがどのようにベイトを捕食しているのか。
最も多いとされているのが、簡単に捕食できるエリアに追い詰める「追い込み型」。ベイトの群れを下から突き上げるようにして捕食する方法です。
まれにライトの照っている足元などで、非常に獰猛かつ繊細に捕食しているシーンを目撃するケースがあります。しかし、派手な捕食ではなく、一瞬にして水中にウロコが散らばるように静かに捕食しているように見えます。
出典:YouTubeチャンネル「釣場速報(つりそく)」詳細ページ
小型だと鋭い歯で小さく噛み切って捕食したり、大型のタチウオの胃からは、丸飲みされたようにベイトの姿が残った状態で発見できたりします。大型になれば一撃必殺で獲物を捕食しているようにも思えます。静かにベイトへ接近して狙いを澄ましてから正確に捕食します。ということは、大型のタチウオほどバイトチャンスは一度だけ。ミスをしても追い食いしてくれるのは、中型タチウオまでという風にも考えられます。

タチウオは、深場と浅場が隣接し、砂や泥の底質と潮通しの良い場所を好みます。
そういった場所は、エサとなるベイトも多いため捕食行動をとりやすく、外敵からも身を守りやすいエリアといえます。ウロコのないタチウオは外傷を受けやすいため、上記のようなエリアであっても、海中に浮遊物(流木やゴミ)が多いと嫌う傾向があり、底質が岩礁帯のエリアや、海藻が非常に多い場所も嫌います。
常夜灯などの明かり周りも比較的好みますが、明かりの真ん中よりも、暗い場所との明暗部の境に身を潜めている印象です。意外な面でいうと、水潮に対しては強く、雨後や河口などを思いのほか嫌いません。
潮流の流速が一定して速いエリアは得意とせず、潮流の緩急ができる地形を好みます。また、急激な濁りが入ったエリアを嫌うのに対し、常に濁っているエリアであれば気にしないという、一言では済ませられない不思議な要素が満載なのがタチウオです。

釣りをする際のポイント
日本列島の広範囲に生息しているタチウオの性格上、ポイントによって差がありますが、一般的にショアから狙えるシーズンは初夏から晩秋くらいです。
例年、海水温が高いことから冬でも釣れることがあります。シーズンの初めは小型から中型が数多く釣れ、終盤に差し掛かると共に大型が出やすい印象です。

時間帯に関しても、釣行するポイントによって様々です。
ただ、比較的高活性な時間帯は夕マズメと朝マズメです! レンジも表層付近が多いので、水深のこともあまり気にせず済みます。
また、水深が10m以上あるディープエリアが絡むポイントであれば、15時ぐらいからヒットする「デイゲーム」が成立することもあります。
大潮は潮位差が大きいわりに潮流があるため、時合が短いとも言われます。潮時表などを参考に釣行日を選べるのであれば、大潮後の中潮以降の小潮回りがオススメです!
これもエリアによって異なるので、行こうとしているフィールドに詳しい方に聞いたり、実際に通ってみてどの潮のどういった時間帯が釣れるのかを検証してみるのもイイでしょう。
曇天や雨天の場合は、光量が少ないので、水中が暗くなる時間帯が早まり、ヒットタイムも早くなる傾向にあります。
また、風や波がない「べた凪」状態よりも、若干風が吹き、波気がある時の方が、ショートバイトが少なくフックアップできるタチウオが多いです。

ハイシーズンになると、想像以上にアングラーで賑わいます。狙いの場所を確保したい場合や落ち着いて釣りをしたい場合は、余裕のある行動を心掛けましょう。
さて、そんなショアからのタチウオゲームでメインとなる2つのポイントの特徴を少しご紹介しておきます。
波止の特長
まず、波止は非常に手軽です。
タチウオの回遊が始まると一斉にボコボコ釣れる時もあり、場所によっては車を横付けできて荷物を持ち歩くこともありません。必要なモノがあれば、コンビニや自動販売機ですぐに買えるなどの利点もあります。
沖堤防の場合
渡船で渡ってしまえば、タチウオパラダイスと言えるほどです。
外海を狙い放題で、ベイトの回遊量も多く、タチウオの回遊前に青物の回遊があるというのもウレシイところですね! 当然ながら沖を狙えるため、タチウオサイズも比較的大きめです。夕マズメ前に渡って、時合の終了とともに帰るという、効率の良いタチウオゲームが楽しめるスポットです。
タックルについて
習性や場所選びに季節など、色々お分かりいただけたと思いますので、今度はいよいよタックルを紹介していきます。
タチウオ専用ロッドを使いましょう。
長さは8~9ftくらいで問題ありませんが、遠投する場合は長い方が有利になります。また、専用ロッドを買うまでもないという方は、手持ちのシーバスロッドやエギングロッド、ライトショアジギングロッドなどでも代用できます。

ワインド X【ダイワ】

ソルパラ タチウオ【メジャークラフト】
タチウオゲームでは、比較的重めのルアーを扱い、飛距離が必要とされます。そのため、3000番クラスのスピニングリールがオススメです。
ただし、リールが大きくなるほど重量も増えるので、ロッドとのバランスを考慮して選びましょう。軽すぎてもアンバランスになることがあるので注意してください。

フリームス【ダイワ】

アルテグラ【シマノ】
タチウオゲームでは、比較的激しいアクションで誘うことが多いので、伸びの少ないPEラインが主流です。操作もやりやすくてオススメです。遠投する必要もあるので、細めのラインが適しています。初心者の方だと0.8号や1号くらいがオススメです。
PEラインを直結にしてしまうと切られるリスクがあるので、リーダーやワイヤーをPEラインに結びましょう。リーダーはフロロカーボンラインの細くて30Lb~40LBくらいが基準ですが好みです。細くなるとルアーの動きが良くなりますが、切られるリスクが上がります。逆に太いとラインブレイクは防げますが、ルアーの動きが損なわれます。

BASIC PE【サンライン】

ジグパラワインド・ワイヤーショートリーダー
タチウオゲームの定番はワインド釣法ですが、近年は4~6g程度の波止用タチウオテンヤにワームを装着して狙うといったスタイルも流行。その他にもバイブレーションやミノー、ジグなどもオススメ。
専用ルアーでなくても、シーバス用ルアーでも代用できます。



これから増々タチウオゲームが面白くなるハズ!
それまでに基本をマスターして、ぜひ挑戦してみてくださいね!