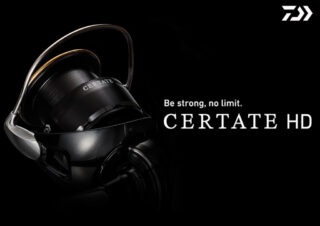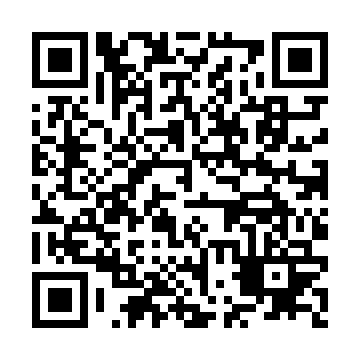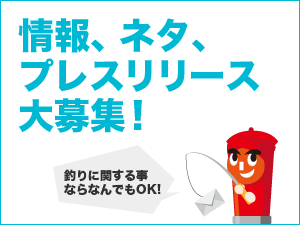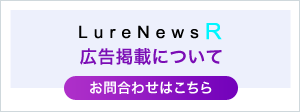いよいよ全国各地で解禁“アユ釣り”。
日本伝統の友釣りなどが代表的ですが、本記事の本題でもあるように、近年ではアユをルアーで狙うという新しいスタイルが注目を集めています。“アユルアー”や“キャスティングアユ”、“アユイング”など、様々な呼び名がありますが、各メーカーからは専用のロッドやルアーなど、関連アイテムが続々と登場しています。
人気の高まりにより、“アユルアー”を楽しめる河川も拡大しており、チャレンジしやすい環境が整いつつあります。そこで今回は「アユルアー入門」と題し、これからチャレンジしてみたい方に向けて基礎を紹介していきたいと思います!

アユルアーにおける注意点
まずは、アユルアーにおける注意点について。
アユルアーを楽しむ上で、まず確認しておきたいのが、その河川でアユルアーが可能かどうかという点です。河川によっては、ルアー釣りを禁止している場所や、リール付きのロッドによる釣り自体を禁止しているところもありますので、必ず公式HPなどで事前に確認するようにしましょう。
また、アユルアーが可能な河川であっても、許可されている区間が定められていたり、ハリスの長さに関する規定など、細かなルールが設定されている場合があります。
こちらも必ずチェックしておきましょう。

ダイワ公式「推奨河川 漁業協同組合一覧」詳細ページはこちら
続いて、注意点は遊漁券の購入!

アユは、各河川の漁業組合が毎年放流活動を行っています。
釣りをする際は、必ずその河川の遊漁券を購入して楽しみましょう。遊漁券は、対象河川周辺の釣具店のほか、コンビニエンスストアで取り扱っている場合も。詳細は各漁業組合の公式HPなどで確認することができます。
同じエリアでは当然、友釣りやコロガシ釣りなど…他の釣りを楽しむ方も多くいます。
特にアユルアーの場合はキャストをするので、エントリーする際は他の釣り人と十分に距離を取り、邪魔にならないよう注意しましょう。お互い気持ち良く釣りができるよう、挨拶や配慮、思いやりの気持ちも忘れずに!

アユルアーはまだまだ歴史が浅く、今後アユルアーが可能な河川が拡大するか縮小するかは、アングラー1人1人の行動に大きく左右されます。
ゴミを持ち帰るのはモチロン、マナーやルールをシッカリ守り、アユルアーを楽しむ人が、今後さらに増えていけば素敵ですね。
アユルアーってどんな釣り?
ターゲットのアユは“サケ目アユ科”に分類される川魚。
大きさは10~30cmほどで、主に川の石などに付着する藻類や水生昆虫などを主食としており、非常に縄張り意識が強いことでも知られている魚です。

アユの友釣りでは、そうしたアユの縄張りに“オトリアユ”と呼ばれる釣りバリを付けたアユを投入し、追い払おうとして、体当たりしてきた個体を引っ掛けて狙います。
アユルアーでは、オトリアユではなくルアーを使用することで、アユの縄張り意識を刺激して誘う釣り方となります。

ちなみに、アユは漢字で書くと“鮎”ですが、一説によると、“場所を占める”ほどの縄張りの強さから、魚偏に“占”と表記されているのだそうです。
狙えるサイズは20cm前後のアユが多く、ブラックバスやシーバスなど、他のルアーフィッシングのターゲットに比べるとやや小ぶりです。しかし、掛かるとその引きの強さはかなり強烈!
というのも、ハリが口ではなく背や腹にかかるため、抵抗感が増し、さらに川の流れと相まって、よりスリリングなファイトが楽しめます。とはいえ、強引に引き寄せてしまうと身切れが起こるため、ロッドのパワーやリールのドラグを調整しなければならないという繊細な一面があるのも魅力です。

狙い方に関しても、やみくもに遠投するのではなく、アユがいそうなポイントを見つけて、そこにルアーを送り込み、誘うのが基本です。アユは水中の石や障害物に付いて、その場所を縄張りとするため、水中の様子を想像しながら狙うのも醍醐味の一つ。そして、イメージ通りにアユが掛かった瞬間の達成感や喜びは格別です!
引きの強さはもちろんのこと、ゲーム性の高さにもハマる人が続出。

タックルについて
近年は、各メーカーからアユルアー専用のロッドが多数登場しています。
ロッドはスピニング・ベイトそれぞれが展開されており、どちらを選ぶかは、使い慣れている方でOKです!

ロッドに関しては、おおよそ8ft前後のモデルが多く展開されており、中規模〜大規模の河川や、幅の広い瀬、流れの強い瀬に対応した10ftクラスのロングレングスモデルも登場しています。最初に選ぶのであれば、オールラウンドに対応できる、7~8ft台のモデルを選ぶのが良いでしょう。また、リールに関しては、スピニングであればおおよそ1000〜2500番クラス、ベイトであればバス用のベイトフィネスや渓流用を流用することが可能です。オススメロッドは以下の通り。




専用ロッドに勝るものはありませんが、他のルアーゲーム用ロッドも流用できます。
流用できるロッドとしては、“バスロッド”や“トラウトロッド”、ソルトでは“メバリングロッド”や“エギングロッド”などが挙げられます。アユを掛けたときに身切れを起こさせないためにも、ティップ部分がしなやかで、さらに程よく曲がる機種を選ぶのが良いです。はじめてアユルアーにチャレンジする場合は、まずは手持ちのロッドを流用し、そこから経験を重ねて専用ロッドにステップアップするというのもオススメです。

ラインは、PEラインとフロロカーボンライン(ナイロンライン)のどちらも使用可能。
PEラインは強度も直線強力も高いため、細い号数を使用することができ、繊細に狙うアユルアーゲームとの相性は抜群。視認性も良く、瀬に入れた時にライン位置を把握しやすいのもメリット。PEラインが不慣れな方やノットを組むのが苦手な方であれば、フロロカーボンラインやナイロンラインをそのまま使用するのもオススメ! フロロカーボンラインであれば3~5Lb、ナイロンであれば5Lb前後が良いとのこと。

アユルアーの種類

アユルアーにも様々なタイプが存在します。
主にミノー系が中心で、その他バイブレーションやジョイントタイプといったモデルもラインナップされています。地形や水深、流れの強さなど状況にあわせて、使い分けるようにしましょう。

DAIWA「アユイング ミノー SS」

DUO「流鮎 VIB」

DAIWA「AYUINGジョイント」
基本的にアユはボトム付近にいるため、ウエイトをプラスしてレンジ調整することも重要。別売りシンカーも展開されているので、常備しておくようにしましょう。

DAIWA「アユイングシンカー」
使用するハリについて
ルアーに次いで釣果に直結すると言っても過言ではない、アユルアーで使用するハリ。
種類は主にチラシ針とイカリ針が代表的で、ハリ先の角度が小さく、ホールド性に優れているのが特長。一度掛かると深く食い込み、ガッチリとホールドします。
カエシがなく、貫通力に優れており、ハリ先も非常に鋭いため、取り扱いには十分注意が必要です。また、河川によってはハリスの長さが規定されている場合もあるため、事前にチェックしておきましょう。

針先が鋭いアユバリですが、釣果を出し続けるには定期的な交換が不可欠。特にアユが潜むエリアは岩や石が多いため、接触やスタックでハリ先がなまってしまうことが多々あります。また複数尾釣った後などもハリ先が潰れてしまいがちなので、こまめにチェックするようにしましょう。予備のハリも十分に用意しておくのもお忘れなく!

DAIWA「アユイングフック」
必要なアイテムについて
ここでは、タックル以外でアユルアーゲームに必要なアイテムを紹介します。
初めからすべてを揃える必要はないと思いますが、中には必携の装備もありますので、ぜひこちらも引き続きチェックしてみてください。
まず必ず用意しておいた方が良い、アユをキャッチするランディングネット。
ネットの選び方に関しては、友釣りなどで使用されるアユ用のネット、もしくは渓流用のモデルがオススメ。ハリが絡みにくいネットの目が細かいモデルをチョイスすると手返し良く楽しむことができます。

DAIWA「アユイングネット V 30」
続いては、釣ったアユを入れておくのに便利な“引舟”。
ルアーアングラーからはあまりなじみのないアイテムですが、友釣り師の方が腰につけて川に流している“船のようなモノ”といえばイメージしやすいかと思います。最近では、携帯性優れた折り畳みができるバッグタイプのモデルも展開されています。

絶対に必要ではありませんが、あると釣った後の手間や効率も上がるので、予算などに余裕があれば用意しておくのがオススメです。

DAIWA「友舟 RX-450W」
また、ネットや引舟を身に着けておけるベルトがあると非常に便利です!
アユベルトがあればネットなども携帯しやすく、そのほかドリンクホルダーなどのツールを取り付けるのにも便利です。特にランディング時に素早くネットを展開できるため、キャッチ率が上がり、手返しも良くなります。友釣り用のアユベルトを流用することもできますし、アユルアー用の専用ベルトも登場しています。
ぜひチェックしてみてください。



DAIWA「鮎ベルト DA-4006 SP」
そして最後は必須のアイテム、偏光グラス。水中の地形の変化や苔の生え具合など、エリアによってはアユがアタックしてくる様子も見ることができます。
装備について
そして重要となるのが、身に着ける装備についてです。
冒頭でも触れた通り、アユは岩や石などに付着した藻類を主食としており、アユがいる場所には苔が生えています。そのため非常に滑りやすく、足元のシューズ類はもちろんのこと、身に着ける装備はしっかりと整えておきましょう。

まず、シューズに関しては苔などでも滑らないウェーディングシューズが最適!
ソールはフェルトタイプ、ピンフェルトタイプを選ぶのがオススメ。モチロン友釣りで使用する“鮎タビ”があればベスト! 瀬などに立ち入る際は足元が見えにくく、思わぬところで足をとられることもあるので、十分に注意するようにしましょう。

DAIWA WS-2502C(フェルトスパイクソール) ウェーディングシューズ

DAIWA DT-2202VR(先丸中割) ダイワタビ
川に入るとひんやりと涼しいですが、夏の日差しは強く日焼け・紫外線対策は必須。
また、下に関してはウェーダー着用もしくはプロテクトタイツ・ゲーターなど渓流で使用する装備をそのまま着用することができます。真夏であればタイツにハーフパンツ、足元はウェーディングシューズのウェットスタイルがオススメです。

DAIWA「NG-300S ネオゲーター」
ポイントの見つけ方
続いては、アユのいるポイントの見つけ方です。
これまで度々触れてきた通り、アユは岩や石に付着した藻類を主食としており、それらが豊富に生えているポイントには多くの個体が付いています。そうしたポイントを最も効率的に見分ける方法が、“良い苔”が生えているかどうかです。“良い苔”とは、以下の画像のように緑色の苔が生えている場所を指します。

そうしたポイントでは、アユが苔の周りを泳いでいる姿も見ることができ、さらに岩などに苔を食べた痕跡、“ハミ跡”も残されています。こうした場所は間違いなくアユがいる証拠でもあるので、ぜひ狙ってみましょう!

アユが居る場所にはこうしたハミ跡が残されています
逆に良くないポイントの例でいえば、苔が生えていない、もしくは苔の色が汚い茶色系のところ。


こうした所では、アユがついていない可能性が高いと言われています。
川に入らずとも、こうしたチョットした違いでも、状況を把握しやすいので、ぜひポイントに入る前にチェックしてみてください。
アユがついていそうな“瀬”を探す
続いて意識すべきポイントとしては“瀬”を探すこと。
前項では、アユがつきやすい苔についてお伝えしましたが、こちらはに関してはルアーを通すべきエリアになります。石や岩などが複雑に入る変化のある瀬にアユは着きやすいと言われています。

まず狙うのは、チャラ瀬やザラ瀬と呼ばれる比較的水深の浅い瀬。
チャラ瀬は、一般的にチャラチャラと流れる水深がひざ下程度の浅めの瀬を指し、ザラ瀬はチャラ瀬よりも若干流れが強めで、水深も膝上から股下くらいの瀬。

瀬の呼び方に関しては、具体的な定義や規定もないので、感覚的なトコロもありますが、比較的に浅く、それでいて水面の所々で波が立っている所を見つけて入るようにしましょう。また、今挙げた瀬はビギナーの方でもエントリーしやすく、それでいて水中も把握しやすいので、アユルアーゲームをはじめるにもピッタリなスポット。
エントリーしやすいとお伝えしましたが、ザラ瀬の一部は流れの強いエリアもあるので、瀬に入るときは十分に注意するようにしましょう。


その他、流れが穏やかながら水量のある平瀬や、波が立っていなく水深のあるトロ場などは、瀬に入らずとも狙えるポイント。その他、水中に障害物や大きな石・岩などが沈んでいるポイントは大型のアユや活性の高い個体が多くついている可能性があるので、忘れずにアプローチするようにしましょう!


動画でも基礎知識を習得!
アユルアーゲームは、川に入りながら楽しめるため、涼しさや季節感も味わえる非常に魅力的な釣りです。それでいてゲーム性も高く、始める方も年々増加しています。
ぜひ、気になっていた方は、この機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?