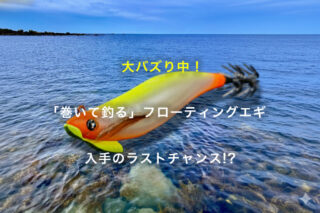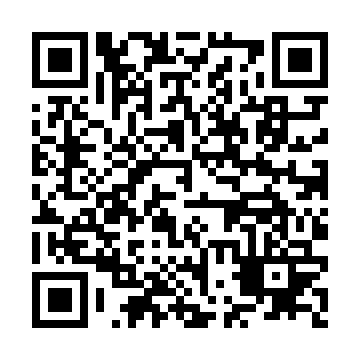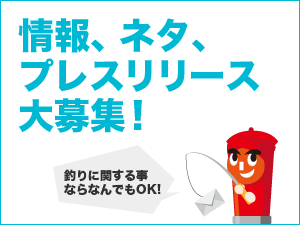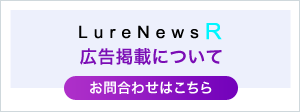今江克隆のルアーニュースクラブR「時代を変えたFFS(フォワードフェイシングソナー)の功罪と審判」 第1255回
FSSの技術を追求すると
このFFS技術は今や間違いなく、「FFS能力=トーナメントの強さ」と言っても過言ではない。
だが、この時代のゲームチェンジャーであるFFS技術を追うがゆえに、アングラーが持つ本来の高い才能を弱体化させてしまうリスクもある。
TOP50参戦1年目にして圧倒的な注目度と結果を残しつつある藤川温大プロは、17歳からFFSは日常から親しめるバスフィッシングの基礎道具とも言える当たり前の存在だった。
同時にFFS技術がトーナメントの最強無双の武器であることを、当時の藤田京弥プロ達のTOP50での圧倒的な強さを見てすでに認識し、身に付け初めていた。
その結果、TOP50参戦1年目にしてトップライバーがひしめくTOP50でも引けを取らない存在感と成績を発揮している。
FFSがまだなかった時代から見れば、新人選手がTOP50初年度を残留権内で終えることは極めて難しいことだ。
しかし、FFSを極めていれば今や初年度から優勝争いを演じられるのである。

デジタルネイティブ、時代の象徴とも言える藤川プロ。16歳の頃から先を見越して修得したFFS技術はTOP50でも屈指の実力だ。

今やTOP50での強さは経験の長さやキャリアではなくなった。今やアメリカ同様、FFSの能力差こそがTOP50での強さの基礎であることは間違いない事実だ。
河野正彦プロの今年の苦戦
だが一方で、河野正彦プロの今年の苦戦は逆にFFS時代を象徴するような部分がある。
それはズバ抜けたサイトフィッシング能力を持つ河野プロは、FFS不要な霞水系や1尾勝負のサイトが極めて有効な生野銀山湖などでは、MLF/BMCのAOYを獲得できるほど傑出した力を持っている。
しかしながら、この数年、TOP50では繰り上げ残留で辛うじて残留は出来ているが、今季は遂に最下位争いになっている。

ずば抜けたサイト能力を持つ河野プロは、流入河川アリの霞ヶ浦戦ではめっぽう強い。だがその才能がFSSを学ぶことによって今年は完全に崩れている。
それは河野プロが今のTOP50では、サイト能力だけでは生き残れないことを痛感し、FFSに真剣に取り組み始めたがゆえの過渡期における逆効果だと言える。
「FFS」と「リアルサイト」はある意味、「究極のデジタル技術」VS「究極のアナログ技術」であり、まさに真逆の存在だ。
正直、アナログ技術に圧倒的に長けているアングラーほど、FFS技術は修得しにくいように思う。
おそらく性格的な部分も大きく影響すると思うが、今の河野プロは無理やりFFSを修得しようと練習の大部分をFFSに費やすことで、彼本来のサイトフィッシングに費やす集中力が分散していると思う。
いわばどっちつかずの状況に陥り、自分本来のポテンシャルも半分以下になってしまっているのだ。
それなら「アナログに徹した方が…」と周囲は思いがちだが、それではもはやTOP50年間では全く歯が立たないことを本人がこの数年で一番痛感してきたからこその今なのである。

FSSを自分のモノにできた時、河野プロのサイト能力はさらに強力な武器となりTOP50・AOYも夢ではなくなるだろう。河野プロが今後態勢で立て直せるかどうかはFFSとどう付き合うかにかかっている。
ある意味、三原直之は本格的なFFS時代が始まる前にそのことをいち早く察し、自分のスタイル、弱点を客観的に見つめ、トーナメントプロを自ら退いたのは英断と言えるのかもしれない。

河野プロと同等、それ以上のサイト能力を持ちながらトーナメントを潔く引退した三原直之。自分自身の適性を一番よく知るがゆえの選択は、今後彼がどのような道を歩むのか、自分もとても興味がある。
藤川温大プロはすでにFFSに弱点がほぼないことから、ライバーだらけのTOP50でもいざとなったら試合を守れる基礎能力が圧倒的に高いと言える。
リアルタイム探査に強いFFSの高い基礎能力があると、逆に探査作業に時間のかかるアナログに割ける時間が河野プロより圧倒的に長くなることもFFSに卓越したプロのメリットでもある。

イマカツにとって初の本格派ライバーである藤川プロから学ぶことは本当に多い。自分が38年もトーナメントの先輩とは思えないほど、その知識には驚かされる。
先にFSSの基礎能力を確立したアングラーの方が、逆にアナログ系のマスターも早いと言うのが自分の見解だ。
現実的に河野プロが苦手なFFS技術で藤川プロに追いつくには最低でも1~2年間、FFSだけで戦い「実戦実績」と言う自信を付けなければ不可能だろう。
それをTOP50の試合内で実行するのは並大抵のことではない。
同じアナログプロの自分がTOP50ライバー達にギリギリついていけるのは、アナログ技術に高度な多様性を持つがゆえ、まだFFSと併用できる守備能力に一日の長があるからに過ぎない。

アナログでの釣りの多彩さ、器用さは自分のスタイルの特徴でもあった。だが今やTOP50ではFFSが標準レベル以上に出来たうえでしか、その威力を十分に発揮しない現実に直面している。
FFS、バストーナメントの今後
FFSの功罪として、三原プロ、河野プロ、そしてTOP50歴戦のベテランプロと言った「アナログスタイルの超人達」の、トーナメントでの居場所を奪ってしまった感は否めない。
アメリカのB.A.S.S選手の年齢比率は分からないが、日本より遥かにバストーナメントの歴史の長いアメリカでは昔からトーナメントは富裕層のオジサンが中心のスポーツフィッシングだっただけにベテラン(高齢者)の比率はまだ高いのかもしれない。
日本でもTOP50だけではなく、バスアングラー全体を見れば、アナログスタイルがまだ圧倒的に多いだろう。
現実的に20代の若者が十分なFFSを装備してバスボートで全国トーナメントトレイルに出るには、最低でも1,500万円程度の初期投資は必要なことからも、FFS支持層はかなり少数の若年富裕層、もしくは人生賭けた借金ダルマのいずれかとも言えるだろう。
だが、未来のバスフィッシングを支える新世代がどちらに憧れを抱くのかは、まだこれからを見ていかなければわからない。
B.A.S.SエリートシリーズがFFS規制を強めた理由の一つに、アナログ世代のFFS反対派プロが、FFSを禁止したらその実力を本当に証明できるのか?という逆の意味もあるのだ。
ウダウダ文句を言うベテランを黙らせるための試金石と言う点において、来年のエリートシリーズの年間成績は日本のトーナメントの今後においても注目に値するものになるだろう。

常にモニターを見ながらのFFSシューティング。その独特の姿に日本でも賛否両論あるが、ベテラン勢が多いアメリカでは日本以上にFFSに対する論争は激しいようだ。
ま、自分的にはやっとTOP50の真ん中程度にライブサイト技術が身について来て、来年あたりがちょっと楽しみになってきたところで、今さらTOP50もFFS規制されたら逆にガックシってのがホンネですわ。
ただ、アメリカみたいにライブサイト対応のルアーばかりになると、プラグ製造が根幹のトーナメントスポンサーメーカーの立場としては結構、微妙な所ですけどね…。

自分が「クジャラ」を溺愛するようになったのも、この手のルアーが最もFFSでモニターに容易に捉えられることに起因している。今年のアイキャストでもFFSに映しやすい毛モノが大流行していた。

アナログ世代最後の希望?青木大介プロが今年AOYを獲得できるか否かは来季に向けて大きな意味を持つだろう。霞ヶ浦のオールスター戦もそういう意味ではFFSレスでのベテランVS若手の審判の場だ。